About us
ふりかえって見ているのは、16~19世紀の琉球の器。 この地に生まれるべくして生まれる形を探る。
陶器工房壹について沖縄のやきものというと、“民芸”をイメージするかたが多いかもしれません。
陶器工房壹の主・壹岐幸二は1986年に沖縄県立芸術大学の一期生となり、後に師となる大嶺實清氏に出会いました。はじめの授業で「沖縄のやきものを見せてやろう」と連れて行かれたのは博物館の蔵。そこで触れた16~19世紀の陶器に惚れて、やきものを志しています。
琉球王府が一国の産業振興として各地に散らばっていた窯を壺屋(那覇)に集めたのは1682年のことです。各地に窯が点在していた時代に「湧田焼」があり、今の沖縄県庁のあたりに窯場が広がっていたといわれます。湧田で名も無き陶工が盛んに挽いた“山茶碗”は、器を手に持ち釉薬をすくいがけるだけの、シンプルで合理的な、機能美の典型です。
戦争によって技術の継承は一旦断絶してしまいましたが、古くに存在した器の形質を紐解くと、琉球という土地の環境条件や、人との関わり合いの様相が、見えてきます。
沖縄は成り立ちの過程がとても大事です。 “奇跡の国”で残されてきたものは愛おしい。 「そんな空気をやきもので伝えられたら」 歴史があって、自然があって、そこに暮らす人がいることで、生まれてくるもの。 原料を最大限に生かし、すっきりとよさを取り出したような形を残したいと陶器工房壹は考えています。 |
|
[作家紹介]
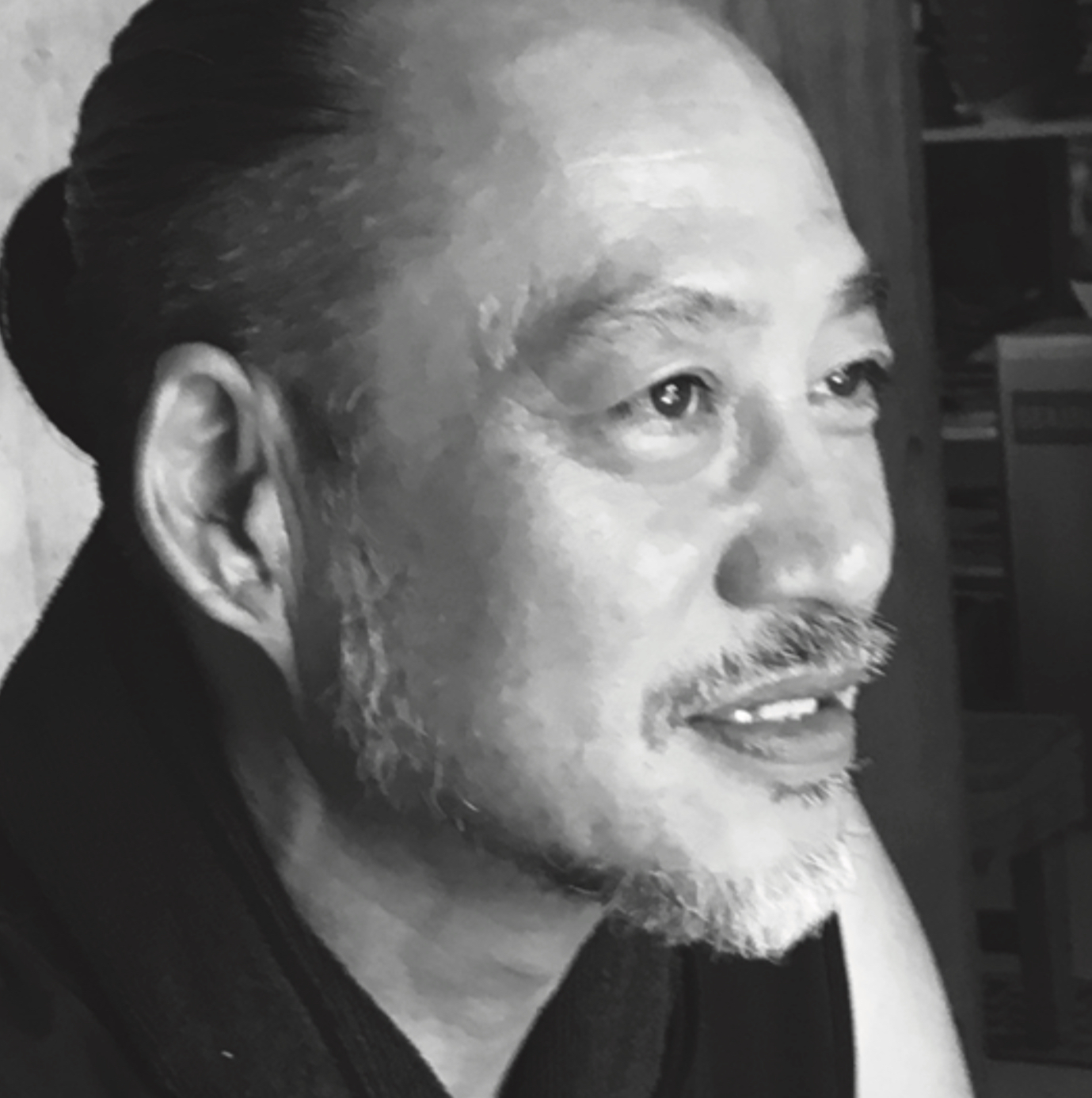 |
陶器工房「壹」での作陶とは別に、壹岐幸二としての個展を開いています。 地層、地殻変動、断崖、城壁、厨子甕(骨壺)、ウタキ、化石(土を科学的に焼くのは化石と変わらない)など、自然や大地をテーマにしてきました。 時には「オスプレイ」など特異なものもつくってしまいますが、ドンと環境に身を任せ心に浮き上がってきたものを形にしてきたことには変わりありません。 |
[略歴]

|



